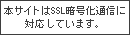閉じる×
共用PCで自動ログイン機能は
共用PCで自動ログイン機能は
使わないでください
職場、学校、ご家族でご利用など
共用でご利用のパソコンでこの機能をお使いになりますと
他の方があなたの情報でログインしてしまう可能性があり
- あなたの代わりに注文をされてしまう
- 購入履歴や登録情報などの情報をみられてしまう
可能性がございます。
自動ログインの解除は会員ログアウトを押していただきますと
次回アクセス時から自動でログインされなくなります