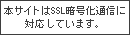このたび高橋龍三郎氏の編集による『パプアニューギニア民族誌と縄文社会−土器型式の解明に向けた基礎的研究−』が、同成社より刊行された。カラー印刷頁を含むB5版392頁の大著で、同氏を含む12名の執筆者から構成されている。高橋氏を中心とした早稲田大学考古学研究室によるパプアニューギニアの民族考古学的調査は2002年8月に始まり、爾来2018年3月まで都合16次にわたって継続されてきた。各次の調査概要については、『史観』誌上にその都度報告されてきたが、本書は17年間に及ぶ民族誌調査を総括した報告書である。民族誌調査報告の体裁を取っているが、副題が示すように縄文社会の実態の究明を念頭に置いた示唆に富む内容となっている。
高橋氏等の民族誌調査の最大の特徴は、考古学者の視点で行った調査手法にある。「考古学的な問いかけに対して、民族学的な調査が解答を与えてくれる」ことを前提として、民族誌調査からの解明を求めている。パプアニューギニアを対象とした目的は、同国の社会階層、複雑化の検討を通して、縄文時代の社会進化史を世界史的視野に立った枠組みで評価することの試みである。パプアニューギニア社会は首長制社会に到達しない「階層化過程にある社会(transegalitarian society)」と見なされており、平等社会ではない。そしてもう一つの目的は、家庭的使用を目的とした素焼き土器の生産の実態を解明し、考古学研究へ援用する点にあった。同じ装飾、形態、装飾がなぜ一地帯に分布し共有されるのか、また一定期間の後になぜ型式変化を引き起こすのか、未解明の大きな課題を探る手立てになることへの期待であった。しかし二つの目論見を同時に研究することは困難であり、後者を重点化する方向が選択された。
本書は第I部6章、第II部4章、第III部2章の計12編の報告・論考と、序章・終章から構成される。パプアニューギニアで調査地に選ばれたのは、ニューギニア東部島嶼部を含むマッシム地域(第I部)と、ニューギニア本島低地部のセピック川中流域(第II部)である。本書ではこの2地域のモノグラフを中心として、第III部でその総括となる縄文社会への接近が論じられている。
「第I部 ニューギニア東部島嶼地域の民族誌」は、マッシム地域の民族誌調査で、第1章〜第6章で構成される。第一次大戦中のマリノフスキーの調査でクラ交易網を発達させた地域として知られており、トーテムを伴う母系制社会とクラン外婚制システムを基軸に、土器交易の発達、配石建造物の構築・利用、土器棺再葬墓などに特徴付けられる。第I部は、イーストケープ(第2章)、ヤバム島・パヒレレ島(第3章)、ワリ島(第4章)、ノルマンビー島(第5章)の対象地域と、マッシム南部における先史土器(第6章)で構成され、執筆は第1章を根岸洋、第2章を中門亮太・平原信崇・比留間絢香・根岸洋、第3章を井出浩正、第4章を中門亮太・根岸洋、第5章を佐藤亮太・隅元道厚・藤根久、第6章を根岸洋の各氏が担当している。
民族誌調査に当たっては、集落配置、社会組織、土器製作・交易、生業、儀礼、立石・列石などに焦点を当てて報告されているが、特にニューギニア本島最東端のイーストケープの調査報告に、全体の約1/3頁に当たる140頁が充てられている。ここでは交易における土器の流れが双方向的ではなく、在地土器が排他的に分布する発信地域と、土器作りを行わず他地域の土器に依存する受容地域、在地で土器作りを行いながらも他地域の土器を選択的に受け入れる地域といった幾つかの在り方が具体的に報告されている。また葬送儀礼である「トレハ」についても、詳細に報告されている(第2章第6節)。トレハは葬送儀礼の直会に擬することができる寄合の祭宴で、同一のクランが一堂に会する。その際に大量の食料が持ち寄られ、調理され、消費されるが、土器が足りない場合、クランの成員女性が集まって土器作りを行うことがあり、製作者間で製作技法や文様などの情報交換が行われるため、クラン単位で土器型式に関する情報が共有される契機となる。合わせて親族関係を通じて他地域からの土器の流入、他地域への土器の流出といった土器移動の機会にもなっており、親族組織を通じた土器型式の広がりが報告されている。また儀礼時の特別食調理では、特定の器種が求められる事象が確認されており、特定土器の広域的分布の背景に儀礼的側面も要因になっている。このように土器型式の分布圏の成立や異系統土器の流通、土器の使い分けに、儀礼体系が大きな影響を及ぼすことが指摘されている。
そしてマッシム地域の島嶼部の事例報告が続いている。その中で「ワリ式土器」の生産地であるワリ島では土器作りが島全体の産業となっており、複数人が効率的に土器製作に携わることもあり、高い規格性をもった土器が流通する。土器型式の流通・分布の背景に製作技術や土器作りの重要度などの社会的背景が存する事例が紹介されている(第4章)。
「第II部 セピック川中流域の民族誌」は、ニューギニア北東部低地部の各部族の土器の製作伝統(第8章)、ヤムイモ栽培と儀礼(第9章)、ハウスタンバラン(第10章)に焦点が当てられている。当該域は仮面や精霊像などの木彫工芸で著名で、前近代的で伝統的な生活様式を残す人々が住む地域として知られ、父系制社会システムを基軸に、限られた村で専業的に土器が作られ、部族間に流通している。執筆は、総論の第7章を高橋龍三郎、第8章第1節イアトゥムル族(アイボム村)を井出浩正、第2節サウォス族(コイワット村)を大網信良、第3節クウォマ族(ミノ村)を山崎太郎、第9章を比留間絢香・山崎太郎、第10章を岩井聖吾の各氏が担当している。この中でアイボム村(第8章第1節)とコイワット村(同第2節)の土器作り、大型の建築物であるハウスタンバラン(第10章)は、興味深い報告となっている。
アイボム村は水上交通網の要衝に位置するパプアニューギニアを代表する土器作り村で、同村の土器は立体的な文様表現や彩色などに優れ、貯蔵用の壺、煮炊き用の鍋、盛り付け用の皿、屋内用のかまど(土器炉)等から構成される。土器作りの大半は女性が担うものの、重要な彩色は男性が担当しており、男女が製作に関わっている。コイワット村では装飾性豊かな尖底鉢である「カマナ」が作られるが、女性が整形・成形し、男性が文様施文と彩色を行う。文様は具象文から幾何学文まで多様なバリエーションが存するが、その多くがトーテムである動植物や自然現象、また精霊を表徴するとされており、土器文様に一定の斉一性が維持されている。土器作りが男女の共同作業である点が、セピック川流域土器作り村の特徴となっている。
ハウスタンバランは「精霊の家」の意で、村の中心部などの要衝に建てられ、村を構成する複数のクランによって共同保有される例が多い。伝統的に建物の使用が許されるのは成人男性のみで、コミュニティを維持するための社会的、儀礼的な場、また彫像や宗教的儀器の保管の場として機能していたが、現在ではその重要性が失われつつある。調査対象となったのは5部族が保有する12村・13棟のハウスタンバランで、共通する属性や機能が認められる一方で、建物の象徴性(男性・女性・戦争)、構造と形態、内部空間の占有・分割構造などに差異も存しており、各部族独自の文化や伝統に基づくことが報告され、ハウスタンバランが伝統的男性優位社会を維持するために必要不可欠な装置であると指摘されている。
「第III部 縄文社会への接近」及び「終章 パプアニューギニア民族考古学的調査の総括」は、これまでの民族誌データを踏まえ高橋氏自身が総括しており、本書の核心をなすものである。
イーストケープ伝統の土器が型式として成立する社会的背景に、製作者がどのような経歴で土器を製作し続け、他からどのような影響を被ったかによって技量や質が異なり、土器型式の系統的な違いを生み出す要因になると推測する。特定クランの技術的特徴が醸成される温床には母系制の居住様式があり、基本的にクラン外に出ないことが技術や知識が保守的にクラン内部に温存され、女性を通じて直系的に継承される。合わせて他の製作者との交流を通じて知識や技術を獲得し伝授されており、トーテム外婚制や儀礼的側面が製作技術や文様が広域に拡散し混交する背景にあることを指摘する。このように一人の土器製作者が身につける技術は血縁関係、婚族、友人関係などを通じて獲得されたものであり、社会的要因が複合的に関係する。従って同一の土器型式が分布する範囲は、基本的に親族関係で結ばれた地理的範囲で、次いで婚姻関係が取り結ぶ結果としてクラン間の技術交流が及ぶ範囲であると規定する。
また土器型式は人間の行動の結果として変化するが、どのような人間の営力が働いたのか。イーストケープ伝統の土器型式に変化が引き起こされる要因には、社会基盤の構造的変動や外部からの影響が推定されるが、その中で女性土器製作者の精神世界に関わる事例が紹介されている。この女性は技術や知識の優れた点以外に、精神世界のリーダー的立場にあり、「土器は私が変える」と豪語する。土器は日常の煮炊きに使われるだけでなく、葬送儀礼の場・遺体処理(伏甕)などでも使用されており、「生」と「死」の両面に係る両義的な代物である。女性の土器製作者たちが精神世界と強い繋がりを持つのは、「死」を巡る様々な局面を念頭に置いて土器を製作するには、強い呪性を備えていないと、葬送に関わる危険な禁忌を乗り越えられないと理解されるからである。この女性は生死両面に関わる土器の本質を知悉しており、土器の技術とは別に、両義的な境界領域の特別な地位を占めたリーダーと目されており、一人の有力な製作者によって土器型式の変化が企図される仮説を提示する。
上記したように、土器型式が成立する社会的背景について、親族構造や出自、婚姻、婚後居住規定、トーテムなどの社会的因子が複合的に関連した実態が明らかにされた。また女性土器製作者が魔女的性格を帯び、精神世界と強い繋がりを有しており、土器型式の変化が無名の多数の製作者が関与することで生じるのではなく、一人の有力な製作者によって企図された可能性が示された。これまで縄文土器研究では全く踏み込んでこなかった領域であり、興味深い指摘である。今後縄文土器の検討を通した具体的な説明が求められるが、縄文土器研究の新たな地平を開いた成果であることは間違いない。これからの研究の進展を期待したい。
伝統的社会が失われつつある中で、17年間に及ぶ調査は貴重な記録となっている。調査がもう10年遅れたら、得られなかったデータもあったという。しかし高橋氏等の民族誌調査は、2019年現地で発生した脱獄事件を契機に中断のやむなきに至った。更にパンデミックが追い打ちをかけたため、この休止期間が本書の編集に割り当てられ、大きな成果として結実したことになる。休止してから5年以上が経過しており、この間現地情勢にも変化が起こっていると思われる。調査報告の中では、今後の課題も幾つか提起されている。パンデミックがパプアニューギニア社会にどのような影響を及ぼしたのか。速やかに調査が再開され、これ等の諸課題が少しでも進展することを願ってやまない。
本書は縄文文化、取り分けその社会構造や土器研究に関心を寄せる研究者にとって必読の書である。縄文文化を研究する上でのヒントが随所に散りばめられており、中でも土器研究者による土器作りのモノグラフは秀逸である。やや高めの価格設定は、読者の理解に配慮してカラー写真を多用し印刷経費が嵩んだためである。編者の高橋氏は縄文社会研究の先導者であり、執筆者の殆どが学生時代に同氏の現地調査に同行し、現在自治体やその関連機関で活躍する気鋭の縄文研究者である。本務を持ちながら本書の作成に従事しており、その労苦は並大抵のことではなかったと推察される。本書は高橋氏の学恩に報いるべく尽力した門下生等の結晶とも言える。その献身的姿勢に敬意を表すると共に、民族考古学の経験が今後の縄文研究にどのような貢献を果たしていくのか注視していきたい。
高橋氏の考古学研究は、2000年4月〜2001年3月のケンブリッジ大学でのサバティカルリーブ(理論考古学研究)が転機となっている。その後2002年にパプアニューギニアの調査が開始されたが、国内での調査が疎かにされた訳ではない。同氏を中心に早稲田大学によって千葉県印西市戸ノ内貝塚の発掘調査(2004〜2010年)や、千葉市加曽利貝塚のデジタル三次元測量・地中レーダー探査(2016〜2023年)が並行して実施されている。民族考古学調査で得られた成果を縄文社会研究に応用する取り組みが絶えず進められており、近年では親族組織や出自・婚姻制度の追究から、ゲノム解析・同位体分析等の自然科学的分野との連携にも研究領域が及んでいる。その成果は2022年3月に『科学で読みとく縄文社会』として、同成社から上梓されている。本書と共に高橋氏の「縄文社会論」の現在地が鮮明になっており、合わせて参照願いたい。