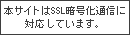城倉正祥氏の新著『唐代都城中枢部の考古学的研究』が刊行された。古代考古学という研究分野に身を置いて、長いあいだ日本の古代都城史を学んできた私などからすると、まさに待望の書であり、またそれ以上に、大いなる驚嘆の書でもある。
本書は城倉氏が近年に公にしてきた3部の研究報告書、すなわち、A「中国都城・シルクロード都市遺跡の考古学的研究」(2017年)、B「唐代都城の空間構造とその展開」(2021年)、C「太極殿・含元殿・明堂と大極殿」(2024年)の、それぞれきわめて充実した内容をもった長大な報告論文を基礎にして、さらに序章と終章を新たに書き加えた、名実ともに大著である。
城倉氏が「都城」に深い見識を備えるに至った経緯は憶測するばかりであるが、氏が一時、奈良文化財研究所の研究員として平城宮・平城京などの日本の古代都城を調査研究の対象としていたこと、そしてその間、奈良文化財研究所と中国社会科学院考古研究所との共同研究としての北魏洛陽城中枢部の発掘調査に、比較的長期に及ぶ協業を経験したことにもあるのではないかと思う。私はそのころ城倉氏の同僚であったが、洛陽に赴いた折、氏の活動ぶりを目の当たりにして心底感嘆したことを憶えている。幾多の制約の中にありながら、城倉氏は中国側の研究者陣と厚い信頼関係を築きあげ、さらには発掘作業に従事している作業員たち−多くは近在の農民であるそうだが−と、実に気さくに、楽し気に談笑しているではないか。あとで聞くと、それは訛りの強い地元の言葉での会話だったらしい。私には、本書は城倉氏のそうした実体験をも奥深い基礎としているのだと思える。
すでに旧聞に属するが、2003年の秋のこと、私は(財)東洋文庫の前近代中国史分野の研究グループの一員として、青山学院大学の田村晃一先生に誘われて、はじめて中国大陸の土を踏んだ。渤海国の遺跡を探訪する旅で、その日は中国・黒龍江省の牡丹江市の旅舎に止宿していた。終日、渤海上京龍泉府の遺跡を踏査した疲れで就寝しようとしていた矢先、今次の渤海行の領導役である金沢学院大学の小嶋芳孝氏が、上京龍泉府の考古学調査の責務を担っている某氏を伴って部屋を訪ねてきた。小嶋氏の通訳を介して尋ねられたことは、この広大な都城遺跡のさらなる解明のために為すべきはなんであるか、と。私は眠気を覚ましながらも即答した。それは大縮尺の詳細な地形図を作成することだ、と。私や、そして城倉氏も関わった平城京の調査研究にあって、1960年代以降作成を続けていた縮尺1000分の1の地形図群は、発掘調査だけでは限りのあるさまざまな解析作業に、はかりしれない貢献を果たしていることは明確に認識されている。しかし、現代の中国にあって、精確な地形図を望むのは至難のことではないかと、実は私自身はかなり悲観的であった。ところが帰国後ほどなく、職場の同僚の一人から、かつて米軍が撮影した衛星写真の入手が可能だと教えられた。早速、ようやく部外秘の封印が解かれたばかりの、1960年代に撮影された渤海上京龍泉府周辺のCORONA軍事衛星写真のフィルムをアメリカ地質研究所(USGS)から取り寄せて、私なりに解析を試みたことがあった(井上「渤海上京龍泉府形制新考」『東アジアの都城と渤海 東洋文庫叢書第64』財団法人東洋文庫、2005年)。
城倉氏が遂行した都城研究では、私のささやかな試みに比べれば格段の進捗を遂げた方法が縦横に駆使され、加えて、氏の的確な解析手法を通じての研究成果は高い信頼度を示すに至っている。氏は研究の方法について、このように宣揚する。「現在の考古学的分析で必要とされているのは公表されている発掘調査報告書の遺構図面を丹念に分析し、歴代王朝によって漸増する尺度(年代の指標ともなる点が重要)を析出し、その尺度をもって遺構の構造を把握する作業である。さらにその造営尺を把握した空間構造をより大きな都城・都市全体の平面配置の中で、UTM座標系や衛星画像を用いて位置付け、遺構の発掘調査を設計論まで昇華させる試みである」(前掲報告書A:9p)と。この揺るぎのない信念に裏打ちされた研究は強靭である。
なぜ「都城」研究なのか。国際ジャーナリストとしても著名な手嶋龍一氏の『スギハラ・ダラー』(新潮社、2010年)という情報小説に「それぞれの通貨には、その国の経済のありようが精緻に投影されているだけではない。通貨とはその時々の国際情勢をくっきりと映し出す鏡のような存在なのだ」という一節がある。私はこの一文の「通貨」を「都城」に、「経済」を「政治社会」と入れ替えれば、実に都城の歴史存在としての本質を言いえていると思う。すなわち都城とは、首都とする国家の政治、軍事、宗教、経済さらに国際関係のありようが凝縮された構築物であり、加えるに、分析・解析に際して客観的に可視化しうる歴史素材でもある。この点において、都城研究は歴史研究の重要かつ不可欠な骨格たりうる案件を具備しているのである。
中国の都城研究を中心に広く世界史的視野で歴史の追究を深化させている妹尾達彦氏は、長く分裂していた中国大陸の華北と華南を隋が統一した6世紀末から唐代にわたる8世紀にかけての時期を、「ユーラシア大陸東部(東アジア)」での「都城の時代」だとする(妹尾「隋唐の王都」『講座 畿内の考古学 第III巻 王宮と王都』雄山閣、2020年)。隋が北朝の覇権を掌握して直ちに造営した首都・大興城と、それを襲用した唐の長安城という、中国史上、空前絶後の最大規模であった都城を規範として、周辺各地域国家でさまざまな様態を伴う都城の建設が展開された時代の謂である。いっぽう日本列島にあっては、7世紀の末、694年に飛鳥から遷都した藤原京が都城の嚆矢であり、以後、平城京、恭仁京さらに長岡京と遷都が続き、794年に遷都が行われた平安京を以って造都の営為の歴史は終焉を迎える。わずか100年の期間に目まぐるしく都城の造営が繰り返されたのである。この転変著しかった点にこそ、日本での都城の歴史ひいては日本古代史の本質を見出しうると考えるが、その案件は置くことにして、城倉氏が解析・考察の対象とする「都城」遺跡は、妹尾氏の言う「都城の時代」の範疇を、時代においても空間においても、はるかに凌駕する。
城倉氏は都城研究に対する基本的視座について、「(都城や宮殿の)遺構の存在形態の比較などの考古学的作業ではなく、実態の見えにくい思想的な解釈から実際の遺構を解釈する方法論には十分な注意が必要だと考える。(中略)もちろん思想的な背景の追究は重要な都城研究のアプローチではあるが、考古学的分野に関して言えば、発掘された遺構自体の丁寧な解釈と比較研究の蓄積こそが、迂遠に見えても、都城の本質や歴史性にアプローチする最も重要な基礎作業だと考える」(前掲報告書B:188p)と自ら規定する。このような確然とした、むしろ峻厳とも映じる姿勢は、あるいはいささか抑制的に過ぎるとの観もありうるが、ややもすれば思考が浮遊しがちな私自身を顧みるにつけ、むしろ潔く、心地よい。
かつて城倉氏がみせた、埴輪分析にみる観察眼の斬新さと鋭利さにも感服せざるをえなかったが、本書で展開されている氏の綿密かつ精緻な議論には、広範囲におよぶ史・資料や調査成果などの博捜ぶりをも重ねると、目をみはるばかりである。
ここでは氏が論究したそれぞれの内容にまで踏み込む余裕はなく、また私はその力量を欠くが、本書には日本とアジア各地域の都城に関わる主要な調査の情報・知見が網羅されている。そして、それぞれに厳密にして的確な評価が付与されているがゆえにいっそう、現在および将来にわたり、都城研究の盤石な基礎的文典として、またかけがえのない学術上の秀書として、広く江湖に推奨されるべきであろう。