第80回 2025.07.15
縄文後・晩期集落研究の諸問題発行元: 六一書房 2025/05 刊行
評者:長田友也 (中部大学非常勤講師)
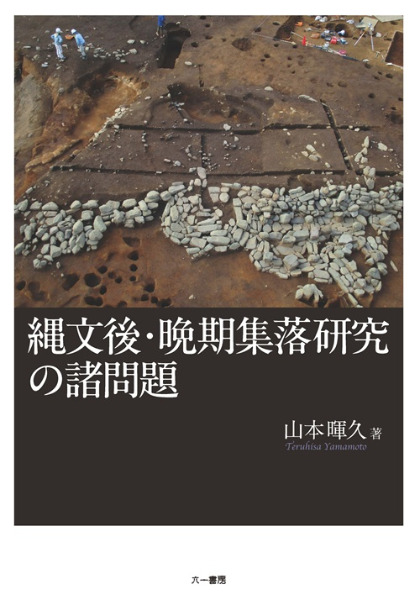
縄文後・晩期集落研究の諸問題
著書:山本暉久 著
発行元: 六一書房
出版日:2025/05
価格:¥16,500(税込)
目次第1章 問題の所在
第2章 後・晩期集落研究の諸問題 関東・中部域を中心として
第1節 環状盛土集落・中央窪地集落
第2節 大形住居・多重複住居
第3節 住居型式と出入口施設の発達
第4節 円筒形深掘土坑
第5節 土坑墓と配石墓
第6節 住居の廃絶と火入れ行
第7節 焼獣骨片撒布の意味
第3章 東北北部・北海道域における盛土遺構、環状列石、周堤墓
第1節 東北北部・北海道の盛土遺構研究の現状と課題
第2節 環状列石(環状石籬・ストーンサークル)
第3節 周堤墓(環状土籬)
第4章 結語
おわりに
挿図出典文献
引用・参考文献
本書は山本暉久氏による、縄文時代後・晩期集落研究に関する意欲的な著作である。本書を手に取って最初に感ずる印象は、なんと厚い専門書であるのかという率直な感想と、本書のすべてが書き下ろしの原稿によるという二つの驚きにある。このような大著となった経緯は序文に詳しいが、令和に入った以後の発掘調査を含め、近年注目される調査事例を網羅し、それらを詳細に分析・検討したとなれば574頁にも及ぶ大著となるのは首肯されよう。さらにその内容は、山本氏がこれまでに上梓された著作で主に扱われてきた縄文時代中期後半から後期前半にかけての時期を大きく飛び越え、自身も「後・晩期とそれ以前の段階は大きく異なる文化として認識すべき」(3頁20行目)とする、後期から晩期におよぶ社会を主題とした集落研究であり、山本氏の新境地といえよう。
山本氏による研究手法については、「おわりに」で詳しく開陳されている。本書の場合、後・晩期の集落に関する研究論文を収集し、メモやコメントを残しながら読破し研究現状を確認する。さらに、関連する関東・中部地方の後・晩期集落遺跡について、住居址の属性分析を中心にデータベース化し、個々の集落遺跡の特徴を分析・検討するというものである。こうした詳細なデータベース作成は、山本氏の研究における真骨頂であり、詳細な資料検討が本書の土台となっている。特に関東・中部域の後・晩期遺跡については、遺跡ごとに丁寧な解説がなされ簡潔にまとめられている。
本書の構成は、「序言」・「例言」にはじまり、「第1章 問題の所在」、「第2章 後・晩期集落研究の諸問題−関東・中部域を中心として―」、「第3章 東北北部・北海道域における盛土遺構、環状列石、周堤墓」、「第4章 結語」と続き、「おわりに」「挿図出典文献」「引用・参考文献」となっている。以下、簡略に内容について触れていこう。
「序言」では、1万年を超す縄文時代の多様な地域性と時期的な変化を指摘したうえで、これまでの山本氏が指摘してきた、中期末を境として後・晩期の文化に大きな違いがある点を強調し、「その大きな違いの意味するものは何なのかを明らかにする」ことが本書をまとめる端緒として示される。その際に、後・晩期社会に対する近年の風潮である「複雑化した社会段階」や「不平等な階層化社会」といった評価を批判し、山本氏が従来指摘してきた、「決して後・晩期社会が複雑化した社会ではなかったことを強く感ずる」とする説をあらためて表明している。
これを受けた「第1章 問題の所在」では、縄文時代について持論である「起承転結史観」(3頁31行目)とする中期段階をピークとする波状の変遷過程を示し、本書で扱う後・晩期を「衰退期から終焉期」に位置付け、従来の晩期停滞史観である「ゆきづまり」論(岡本・戸沢1965)を肯定的にとらえる。これに対し、近年指摘される晩期停滞史観に対する見直し論を批判的に取り上げ、その課題を列挙したうえで「ゆきづまり」論を再評価する立場を表明する。その論拠となるのは、関東・中部域における晩期後葉以降の集落・遺跡数の激減化現象の評価にあり、これを説明するには後・晩期を衰退・終焉期と捉えるのが適しているという視点である。その前提として、「集落規模の大小は、その時代・時期の生産活動と、それに伴う食糧獲得の多寡に左右される」(5頁7-8行目)とする生業史観がある点も述べられている。山本氏が批判する後晩期社会の複雑化や階層化と併せ、縄文時代後・晩期社会の特質について論ずるにあたり、関東・中部域を中心とした後期中葉から晩期を中心とした集落研究と、東北北半部から北海道の盛土遺構・環状列石・周堤墓を対象に研究現状と課題を把握し、その地域性を明らかにすることを本書の目的として掲げている。
続く「第2章 後・晩期集落研究の諸問題」は、約400頁にも及ぶ関東・中部域における後・晩期集落の検討であり、本書の根幹をなす。その内訳は、第1節 環状盛土集落・中央窪地集落(119頁)、第2節 大形住居・多重複住居(34頁)、第3節 住居型式と出入口施設の発達(37頁)、第4節 円筒形深掘土坑(40頁)、第5節 土坑墓と配石墓(102頁)、第6節 住居の廃絶と火入れ行為(25頁)、第7節 焼獣骨片撒布の意味(22頁)からなる。各節の内容については、具体例が挙げられ詳細に分析がなされており、大部な論考となっているため、ここでの詳述は省略させていただく。近年の調査事例を含め、各遺跡の遺構図・遺構配置図や出土遺物が提示され、関東地方の後・晩期を知るうえで良質な案内書としても有効である。是非、手に取ってご覧いただきたい。本章を通じての関東・中部域の後・晩期集落の特徴については、千葉県域を中心に、茨城県・栃木県・埼玉県域の東部関東に広がった環状盛土集落、西部関東から北関東・群馬県域および山梨・長野県域、伊豆半島域に及ぶ柄鏡形敷石住居・配石遺構・配石墓からなる配石集落、両者の接触地帯である武蔵野台地〜下末吉台地にみられる中央窪地型集落といった、顕著な地域性を示す点が挙げられている(243頁2-5行目)。こうした関東域における地域性の明示は、本書の目的でもあり大きな成果といえよう。
前章で扱った関東・中部域との比較検討となるのが、「第3章 東北北部・北海道域における盛土遺構、環状列石、周堤墓」である。その視点となるのは、「北東北〜北海道域の後・晩期のありかたについて、関東・中部域との対比において、その地域性とその背後にある共通意識を探ることが必要である」(397頁17-18行目)というものである。本章は実例の具体的な検討ではなく、既存研究を丁寧に整理したうえで、山本氏の視点により各論考の独創性・論点を指摘しつつ、課題について的確に批評が加えられている。その構成は、第1節 東北北部・北海道の盛土遺構研究の現状と課題(10頁)、第2節 環状列石(36頁)、第3節 周堤墓(33頁)からなる。盛土遺構については、盛土遺構の定義をあらためて課題としたうえで、東北北部〜北海道の盛土遺構が早期後葉より通時的かつ広域にみられる点において、関東域との違いを強調する。環状列石については、既存研究における環状列石の成立過程に関する解釈や掘立柱建物址群とからめた性格論などが的確にまとめられており、山本氏自身は地域ごとの独自性を評価したうえで、環状列石の自体の意義をとらえる必要性を説く。周提墓についても、環状列石とどのように関係するかという成立過程と、階層社会と関連する被葬者の社会的位置をめぐる課題について私見を含めて整理がなされている。
第4章 結語では、本書で分析・検討された内容が簡潔にまとめられている。縄文時代後・晩期の関東・中部域に限っても、地域性豊かな様相・特性を持って変遷を遂げており、こうした時空的な特性を無視して「縄文時代(文化)」を論ずることは不可能に近いとしている。なぜそうした軌跡を辿ったのかについては、不明な点が多いものの「第二の道具」と呼ぶ祭祀・呪術具の発達とともに、後・晩期は祭祀・儀礼の発達した社会へと変貌している点を強調する。その上で、こうした後・晩期における社会の変化を「階層化社会」や「社会の複雑化」とする見方に対して、一貫して否定的な立場をとり、時代の衰退化を示すものが、第二の道具の発達をはじめ、本書で取り扱った後・晩期集落に顕在化した諸現象であったとしている。
以上のように、本書では東日本を主とする縄文時代後・晩期社会の実態について、山本氏独自の視点によって膨大な遺跡資料が詳細に分析・検討されており、後・晩期の集落遺跡の実態がまとめられている。したがって、後・晩期の集落遺跡・社会論研究のみならず、後・晩期遺跡の基礎となる資料集成とでもいうべき一面もあり、後・晩期研究における良質な概説書といえよう。本書によって、後・晩期社会の実態が一定程度明示されたわけであるが、「結語」によれば本書はその序章に過ぎないようである。本書で明らかになった特性を踏まえた「後・晩期社会論」についての開陳が心待ちにされる。
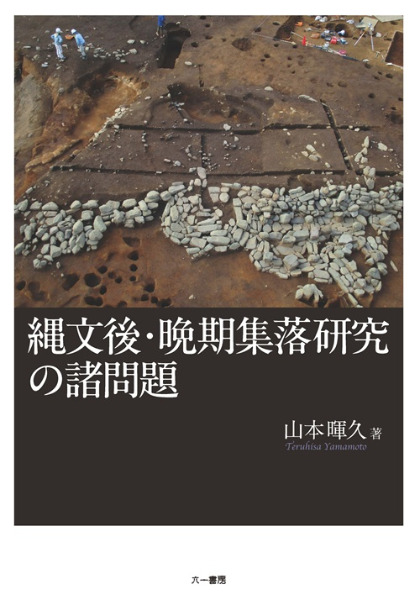
縄文後・晩期集落研究の諸問題
著書:山本暉久 著
発行元: 六一書房
出版日:2025/05
価格:¥16,500(税込)
目次第1章 問題の所在
第2章 後・晩期集落研究の諸問題 関東・中部域を中心として
第1節 環状盛土集落・中央窪地集落
第2節 大形住居・多重複住居
第3節 住居型式と出入口施設の発達
第4節 円筒形深掘土坑
第5節 土坑墓と配石墓
第6節 住居の廃絶と火入れ行
第7節 焼獣骨片撒布の意味
第3章 東北北部・北海道域における盛土遺構、環状列石、周堤墓
第1節 東北北部・北海道の盛土遺構研究の現状と課題
第2節 環状列石(環状石籬・ストーンサークル)
第3節 周堤墓(環状土籬)
第4章 結語
おわりに
挿図出典文献
引用・参考文献
こちらもおすすめ
1 /
